はじめに
日本の農業は、高齢化、担い手不足、そして気候変動といった多層的な課題に直面しています。こうした課題を解決するためのカギとなるのが「スマート農業」です。本報告書では、2025年度における最新のスマート農業実証事業の全体像を、政策連携や補助金制度を中心に徹底解説します。
スマート農業実証事業の概要と政策目標
2031年までにスマート農業技術の活用割合50%以上へ
スマート農業実証事業は、最先端のロボット技術、AI、IoTなどを活用し、日本の農業の生産性向上と持続可能性の確保を目指す国家プロジェクトです。2019年から開始されたこの事業は、2025年までに全農業者がデータを活用した農業を実践することを目標としています。さらに2031年までにはスマート農業技術の活用割合を50%以上に引き上げる長期目標も設定されています。
政策的位置づけと2025年度予算
2025年度(令和7年度)には、スマート農業関連予算として約35億円が計上されており、補正予算と合わせて154億円の大規模投資が行われています。特筆すべきは「スマート農業技術活用促進集中支援プログラム」(予算410億円)の新設であり、これによりスマート農業の社会実装が大幅に加速することが期待されています。
スマート農業技術活用促進法の枠組み
2024年10月に施行された「スマート農業技術活用促進法」は、スマート農業の社会実装を法制度から支える画期的な法律です。この法律に基づき、主に二つの計画認定制度が運用されています。
認定制度の概要
- 生産方式革新実施計画:農業者がスマート農業技術を活用した生産方式の革新に取り組む計画
- 開発供給実施計画:事業者がスマート農業技術の開発・供給に取り組む計画
すでに生産方式革新実施計画については11件が認定されており、農業現場での先進的な取り組みが始まっています。
認定の申請方法と窓口
認定を希望する際は、計画開始予定時点から十分な時間的余裕をもって、地方農政局等へ事前相談を行う必要があります。申請は管轄する地方農政局や北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局にメールで提出します。各地域の担当窓口は以下の通りです:
- 北海道農政事務所(北海道)
- 東北農政局(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
- 関東農政局(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)など、全国9つの窓口が設置されています。
実証事業の全国展開状況
スマート農業実証プロジェクトは全国各地で展開されており、令和元年から令和5年までの間に計217地区が採択されました。これらの実証地区は北海道から鹿児島まで広範囲に分布し、水稲、畑作、露地野菜、施設園芸、果樹、茶、畜産など多様な農業分野をカバーしています。特に中山間地域などの地域特性に応じた実証も積極的に行われています。
地域特性に応じた実証事例
特筆すべき実証事例として、高知県安芸郡北川村および安芸市におけるゆず農園でのローカル5G活用プロジェクトがあります。このプロジェクトでは以下の3つのソリューションが検証されています:
- 自動防除ソリューション:4K360°カメラやスマートグラス等を活用したモバイルムーバー(運転台車)による自動運転で、防除・草刈り作業を自動化
- 新規就農者遠隔指導ソリューション:ローカル5Gネットワークを介して遠隔地から効率的な指導を実現
- 機器のシェアリングサービス:生産者の導入負担軽減のため、機器の共同利用やサービス事業者による遠隔監視・指導を実現
活用されている先端技術とその効果
スマート農業実証事業では、様々な先端技術が活用され、顕著な効果を上げています。
ロボット技術の導入事例
ロボットトラクターや自動野菜収穫ロボットなどのAI農業ロボットの導入が進んでおり、実証では作業時間が75%削減された事例も報告されています。特に農薬散布ドローンは、従来の手作業と比較して大幅な省力化を実現し、中山間地域での作業効率化に貢献しています。
AI・IoT技術の農業応用
AIによる病害予測システム「プランテクト®」やドローンを活用した葉色解析AI「いろは」など、データ駆動型の意思決定支援ツールが普及し始めています。長野県のレタス生育予測AIシステムでは予測精度±1.9日という高精度を実現しており、収穫計画の最適化に大きく貢献しています。
データ連携プラットフォーム
農業データ連携基盤(WAGRI)は2019年から運用され、気象、農地、肥料等のデータやAPIを提供しています。2025年度には「農林水産データ管理・活用基盤強化事業」が公募開始され、データ標準化やAPI連携のルール作り、新サービス開発が支援されています。また、スマートフードチェーンプラットフォーム(ukabis)は生産から流通・販売までのデータ連携で農産物の価値向上を目指しています。
補助金制度と支援体制
2025年度のスマート農業支援には、多様な補助金制度と支援体制が整備されています。
認定事業者への優遇措置
- 補助事業での優先採択:「生産方式革新実施計画」認定事業者は20以上の補助事業で優先採択
- 長期低利融資:日本政策金融公庫からの融資(償還期限25年以内、据置期間5年以内)
- 税制優遇:設備投資時の特別償却
- 登録免許税の軽減
- 研究開発設備の利用:農研機構の研究開発設備利用が可能
地方自治体レベルの補助金制度
地方自治体レベルでも独自の補助金制度が展開されています。例えば宮城県登米市では、ドローンや自動操舵機器等の導入に対して30%以内(上限50万円)の補助金制度を設けています。申請から交付までは以下の5段階のプロセスで進みます:
- 申請書の提出(申請者→市)
- 交付決定通知書の送付(市→申請者)
- 事業実施(申請者)
- 完了後、実績報告書の提出(申請者→市)
- 完了検査、補助金の支払い(市→申請者)
政策間連携の現状
スマート農業実証事業は、他の政策との連携により相乗効果を生み出しています。
「みどりの食料システム戦略」との連携
環境負荷低減とスマート技術の両立を目指す「みどりの食料システム戦略」との連携では、ドローンや自動水管理システムを活用した省力化と環境保全の両立が図られています。
省庁間連携体制
「スマート農業技術活用促進法」を軸に関係府省庁連絡会議による一体的推進体制が構築され、省庁間連携が強化されています。農林水産省の次期基本計画では「食料システムのあらゆる場面でのDX推進」が明記され、WAGRIの活用やデジタル人材育成と連動した政策展開が進行中です。
スマート農業の成功事例
AIを活用したイチゴ栽培システム
AIを活用したイチゴ栽培システムでは、収穫量50%増加、品質向上、農薬使用量削減という三重の成果を達成しています。環境データと生育状況のリアルタイム分析により、最適な環境制御を実現しています。
大規模水田経営の革新
大規模水田経営では、ロボットトラクタ・田植機の導入により18%の省力化を実現し、データに基づく精密な施肥設計により収入が10%増加した事例が報告されています。こうした成功事例は、他地域への横展開も進んでいます。
まとめ
2025年度のスマート農業実証事業は、法制度の整備、予算の拡充、技術の進展により大きく飛躍しようとしています。特に「スマート農業技術活用促進法」に基づく認定制度と優遇措置は、農業者や事業者にとって大きなチャンスとなっています。地域特性に応じた多様な実証を通じて、日本農業の生産性向上と持続可能性の確保が進むことが期待されます。
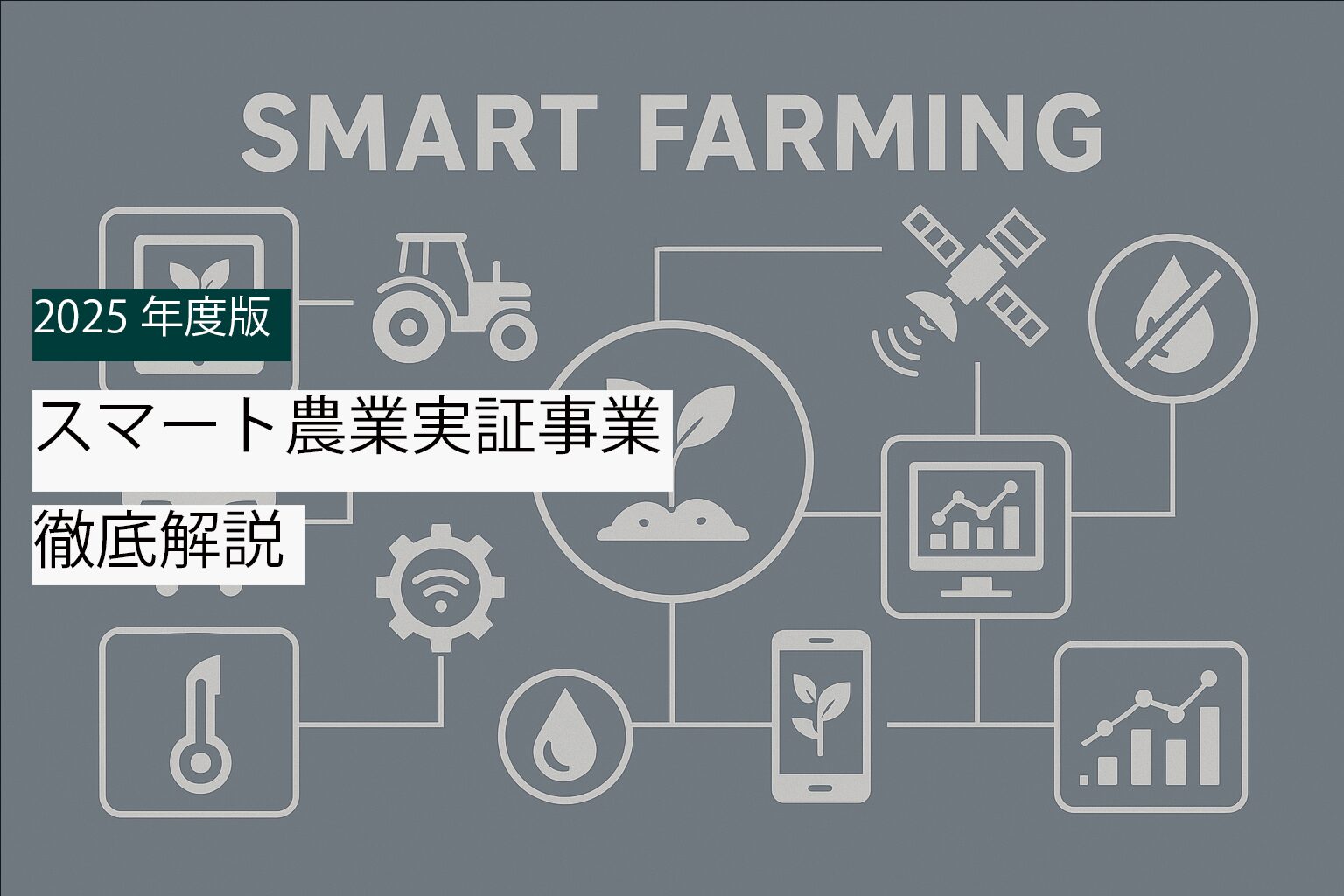


コメント